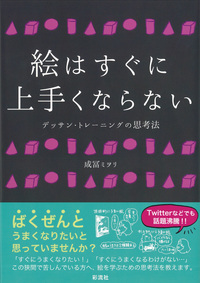【2023年11月4日配信】
考えることがなぜ大切なのか





小を積めば即ち大と為る.『報徳記』富田高慶1856
二宮尊徳翁曰く
「励精小さなる事を勤めば大なる事必ずなるべし。
小さなる事をゆるがせにする者、大なる事必ず
できぬものなり」
読書のすすめ 背負い歩き考える二宮金治郎
ロダンの『考える人』よりもりっぱに思える
薪を負いて名定まる
損得から尊徳の世へ
哲学の時代へ(第14回)
以下の文はkyouseiさんという方のnote
にある文です。偶然みつけ共感するものが
ありこれまで何度か勝手にその文を紹介し
てきました。どこのどなたかまったく存じ
上げませんが、またお叱りを受けるかもし
れませんが、本日掲載の文をご紹介します。
(当講座編集人)

本当の哲学とはなにか
note での投稿も長くなった。 連続投稿が
370を超えたようだ。そんなことはどうで
もいいことだが、ぼくはこれまで「哲学」
だと思って書いていた記事は、「本当に哲
学なのだろうか」と思うことがよくある。
皆の言う「哲学」は、「○○哲学では…」と
難しい話をよく知っている。
ぼくはというと、思考を治療的に使って現
状の維持、回復を狙うものだ。
「何が不満か」「何がそうさせるのか」と
いった答えを探すものだ。だから「治療的
哲学」と銘打っているのだが、はたしてそ
れは哲学なのだろうかと思うこともある。
ぼくの哲学は「結果が全て」であり、再現
性も求める。結果が出ないとすれば、やり
方がまずかったとすぐに修正する。自分自
身を実験台にして確かめるのだ。
難しい話を好まないのは「使えない」から
だ。使えないものは真理ではないと考えて
いる。
だからといって、ぼくの視野が広いかとい
えばそうではなく、個人という狭い世界観
をどう変えるかといったものだ。
「大したことないな」と思われるだろうが、
では、誰がこれまでそのことに挑戦してき
ただろうか。
他人の褌で相撲を取る話ならいくらでもあ
る。傍観者という意味だ。
ぼくの哲学には答えがないかもしれない。
変更し続けるからだが、これは脳の機能に
関連することで重要なのである。
心は脳とは無関係のように言う人もいるが、
認知症の状況を見ても、脳死の話を聞いて
もそう言えるだろうか。言えない。
考えることを考えることが哲学だとぼくは
認識しているので、とりあえず哲学なのだ
ろうけれど、個から全体へとつながる哲学
を目指している。
受け売りの哲学はしないつもりだ。もし、
ぼくの哲学と偉い哲学者と意見が「たまた
ま」一致した時は、ぼくが偉いのではなく
「真理」が偉いのだとわかっていて欲しい。
〈小社推薦note〉 何よりも問いの立て方がすばらしい

当講座記事NO.273から
「石」も流れる
手取川(石川)
茨城中学校1年 佐藤 和さん
石川県立大学 百瀬 年彦さん
白山の石が手取川を流れ砂となって羽咋の千里浜へ
千里浜海岸・渚を車で走れる世界で数ヶ所の砂浜
2026.1.1 木偶乃坊写楽斎さん撮影
きょうの氷見海岸
立山連峰から初日の出
初日を浴びる不二 2026.1.1 於 国立市
飯塚 恵さん撮影
2025.12.24 木偶乃坊写楽斎さん撮影
大公孫樹に止まる枝ガラス 立派な姿
越中おわら節歌詩
花も実もない 枯れ木の枝に
とまる鳥こそ おわら 真の鳥
能登半島地震からの復興を願う250発
2025.12.20
〈小社推薦図書〉
岩崎武雄著『正しく考えるために』
(講談社現代新書、1972)
岩崎武雄著『辯證法 -その批判と展開-』
(東大学術叢書、1954)
西田哲学批判
マルクス主義哲学批判
ヘーゲルの弁証法
キェルケゴールの弁証法
存在の弁証法
認識の弁証法
自覚の弁証法
「弁証法は現在では一般に矛盾の論理すなわち
形式論理学に言う矛盾律を否定する全く新し
い論理として考えられているが、実はここに
われわれの検討すべき根本的な点が存在して
いるのではないかと思うのである。」
「弁証法論者達がこの点を全く看過してひたす
ら弁証法を以て全然矛盾律を否定する新しい
論理であると考え、これこそ一切の問題を解
決する強力な論理であるとなしているのは極
めて非哲学的な態度であると言わねばならな
い。」
2025.12.19
「思う」と「考える」は違う
感情を言葉化する努力も大切
2025.12.17 佐藤章さん

ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ著
『ヴィルヘルム・マイスターの修業時代』
『ヴィルヘルム・マイスターの遍歴時代』
(岩波文庫、2000)
カントの教え子、カント哲学を批判
2025.12.11 木偶乃坊写楽斎さん撮影
きょうの氷見漁港
灯台の右に立山、左には劔岳
2025.11.27
2025.11.26
2025.6.25 Japan ARTnews
2025.11.25
訳の分からない理屈に惑わされない
当講座記事NO.429、427、425から
2025.11.21・22 木偶乃坊写楽斎さん撮影
しぐれにけぶる大公孫樹と氷見漁港
植樹681年 国指定天然記念物 1926年指定
樹高36㍍、幹周り12㍍、秋に1000㍑の実を結ぶ。
地上5㍍あたりから大小無数の気根が垂れている。
2025.11.20
2025.11.12 木偶乃坊写楽斎さん撮影
けさの日の出
立山連峰 富山湾 唐島 於氷見海岸
2025.10.21
2025.10.19 木偶乃坊写楽斎さん撮影
樹高36㍍、幹周り12㍍、秋に1000㍑の実を結ぶ。
地上5㍍あたりから大小無数の気根が垂れている。
2025.10.18 木偶乃坊写楽斎さん撮影
きょうの氷見海岸 日の出前
2025.10.16
揺るぎない信念は個人の利益よりも
全体の利益を優先する考えによって
生まれる。
信念は行動を促し心に自由を与える。
真のエリートがこれまで世界にどれだけいたのか
真の大衆がいたからこそ世界がまだ存在している
2025.10.11 木偶乃坊写楽斎さん撮影
きょうの大公孫樹
2025.10.1
善を知りながら善を行わない
悪人支配の世界に生きるには。
2025.9.30 木偶乃坊写楽斎さん撮影
きょうの大公孫樹
2025.9.29
2025.9.28
2025.9.28 木偶乃坊写楽斎さん撮影
きょうの富山湾と比美乃江公園
左右問わず「自分が、自分が」
と声高らかに叫ぶが多いなか、
人心を高め合う真実への道程。
2025.9.26
小を積めば即ち大と為る.『報徳記』富田高慶1856
二宮尊徳翁曰く
「励精小さなる事を勤めば大なる事必ずなるべし。
小さなる事をゆるがせにする者、大なる事必ず
できぬものなり」
2025.9.16
2025.9.15
あらゆる事象における価値判断を高める努力
権威に頼らない
自分を失わない
2025.9.12
2025.9.9
きょうの大公孫樹 植樹681年
2025.9.9 木偶乃坊写楽斎さん撮影
「樹」-卒業制作- 金沢美術工芸大学4年 青木春美
2025.9.8
1951.9.8 中露の反発もかった桑港講和条約調印 同日この調印直後に日米安保条約も調印された
以来中朝露との真の平和交渉は閉ざされたまま
参考
2012.12.22 日経新聞
2025.9.6
参考
2025.9.6 木偶乃坊写楽斎さん撮影
きょうの富山湾 氷見海岸から
当講座記事NO.208から
西田幾多郎作
天地(あめつち)の 別れし 時ゆ
よどみなく ゆらぐ
海原 見れど 飽かぬかも
打ちわたす 大海原に 夕日入り
漕ぎ行く船は
見るに さやけし
大伴家持作
立山(たちやま)の雪し消(く)らしも
延槻(はひつき=早月)の
川の渡瀬(わたりぜ)鐙(あぶみ)
浸(つ)かすも
『万葉集』巻第十七
(立山の雪が消えていくらしい。
早月川の渡り瀬で、馬の鐙が水に
つかっている。)
208 哲学の時代へ(第2回)
2025.8.31
参考
他人の犠牲にならない生き方
他人を犠牲にしない生き方
藤森かよこ訳
(ビジネス社、2004)
2025.8.24
2025.8.15
2025.8.7
新しい価値の創造
「芸術はその本質が理解されたとき
人類全体のものになる」
2025.8.2
2025.8.1
いかにしたらそのような判断力を持てるか
2025.6.3・4
〈小社推薦論文〉
カント『純粋理性批判』(1781年)
〈小社推薦図書〉
岩崎武雄著『正しく考えるために』
(講談社現代新書、1972)
岩崎武雄著『辯證法 -その批判と展開-』
(東大学術叢書、1954)
西田哲学批判
マルクス主義哲学批判
ヘーゲルの弁証法
キェルケゴールの弁証法
存在の弁証法
認識の弁証法
自覚の弁証法
「弁証法は現在では一般に矛盾の論理すなわち
形式論理学に言う矛盾律を否定する全く新し
い論理として考えられているが、実はここに
われわれの検討すべき根本的な点が存在して
いるのではないかと思うのである。」
「弁証法論者達がこの点を全く看過してひたす
ら弁証法を以て全然矛盾律を否定する新しい
論理であると考え、これこそ一切の問題を解
決する強力な論理であるとなしているのは極
めて非哲学的な態度であると言わねばならな
い。」
2025.4.24
『現象学』
(勁草書房、1985)
米盛裕二著『アブダクション
仮説と発見の論理』
(勁草書房、2007)
2023.12.30
「新しい理論があらわれると、まず、不合理だと
いって攻撃される。次に、それは真理だと認めら
れるが、わかり切ったことで取るに足らないこと
だといわれる。最後に、それはきわめて重要なも
のになって、初めにそれに反対した人々も、その
理論は自分たちが発見したのだといい張るまでに
なってくる。」
ジェームズ氏の言われるとおりではあるが、
普遍性あるものであれば、そのような形で
広められることが普遍性や普遍性に近いこ
との証左となり、むしろ喜ぶべきことでは。
結果に貢献できればそれでよいと考えるが。
広めている人や広められている人の人間性
が問われるにしても。 (当講座編集人)
2025.7.22
参考
2025.4.23
2025.3.17
カトリーヌ・マラブー著
『ヘーゲルの未来
可塑性・時間性、弁証法』
西山雄二訳
(未来社、2005)
『泥棒! アナキズムと哲学』
(青土社、2024.7)
参考
『論語』学而時習之不亦説乎
2025.7.12
2025.7.12 行田池傍の青葉のモミジ 氷見市 撮影者・木偶乃坊写楽斎さんお気に入りの樹
2025.7.6
2024.10.23 チェン・スウリーさん解説・考察
2025.7.5
2025.7.2 チェン・スウリーさん解説・考察
「成り上がりと失墜の人生」
-貴族社会とイギリスの戦争を壮麗に描く-
参考
当講座記事NO.404、416から
政治関連有名人ネット人気度番付小社発表
横綱 深田萌絵 立花孝志
大関 飯山陽 有本香
関脇 警察官ゆり さとうさおり
小結 さゆふらっと さや
前頭 ひろゆき へずまりゅう
前頭 ホリエモン ほんこん
前頭 パックン 細川バレンタイン
前頭 野口健 ケント・ギルバート
前頭 見城徹 モーリー・ロバートソン
前頭 金美齢 リチャード・コシミズ
前頭 エンドゥ デーブ・スペクター
前頭 ロンブー淳 ペマ・ギャルポ
前頭 デヴィ夫人 フィフィ
前頭 今井絵理子 英利アルフィヤ
前頭 今井光郎 山谷えり子
前頭 筒井義信 山尾志桜里
前頭 藤井実彦 山田宏
前頭 石井啓一 山口敬之
前頭 櫻井祥子 山中泉
前頭 櫻井よしこ 山根真
前頭 桜井誠 増山誠
前頭 川裕一郎 丸山穂高
前頭 川田龍平 片山安孝
前頭 川中だいじ 片山虎之助
十両 上川陽子 片山さつき
十両 笹川陽平 鳩山由紀夫
十両 細川護熙 村山富市
十両 井川意高 青山繁晴
十両 松川るい 山東昭子
十両 大川宏洋 山口那津男
十両 立川志らく 山口真由
十両 江川紹子 山本朋広
十両 丸川珠代 河井案里
十両 玉川徹 河合悠祐
十両 及川幸久 河添恵子
十両 笹川博義 河野太郎
十両 長谷川幸洋 河村たかし
幕下 吉川里奈 梅村みずほ
幕下 中川郁子 杉田水脈
幕下 佐川宣寿 葛城奈海
幕下 佐藤優 佐波優子
幕下 高市早苗 水島総
幕下 高須克弥 内海聡
幕下 高橋はるみ 浜田聡
幕下 リハック高橋 藤井聡
幕下 高橋洋一 藤岡信勝
幕下 高見千咲 林千勝
幕下 高木毅 広瀬めぐみ
幕下 高木かおり 麻生太郎
幕下 高木啓 鳩山二郎
幕下 高岡達之 田崎史郎
幕下 小林鷹之 橋本五郎
幕下 小谷哲男 新田八朗
幕下 小池百合子 小泉進次郎
幕下 小泉悠 中村逸郎
幕下 泉房穂 八幡和郎
幕下 泉健太 福山哲郎
幕下 古市憲寿 古舘伊知郎
幕下 古川雄嗣 三枝玄太郎
幕下 古川俊治 玄葉光一郎
幕下 古川元久 鳩山紀一郎
幕下 須藤元気 玉木雄一郎
幕下 齋藤元彦 齊藤健一郎
幕下 島田紳助 須田慎一郎
幕下 成田悠輔 松本誠一郎
幕下 花田紀凱 田原総一朗
幕下 竹田恒泰 篠原常一郎
幕下 門田隆将 茂木健一郎
幕下 黒田東彦 小泉純一郎
幕下 野田佳彦 野口聡一
幕下 岡部芳彦 渡部陽一
幕下 菅義偉 鈴木俊一
幕下 菅野完 大前研一
幕下 生稲晃子 萩生田光一
幕下 池上彰 手嶋龍一
幕下 岩上安身 石丸伸二
幕下 神保哲生 宮台真司
幕下 神谷宗幣 韓鶴子
幕下 田母神俊雄 鶴保庸介
幕下 橋下徹 野田聖子
幕下 橋本岳 橋本聖子
幕下 三橋貴明 橋本琴絵
幕下 三浦瑠麗 阿比留瑠比
幕下 三原じゅん子 シャドウ岩橋
幕下 武見敬三 自見英子
幕下 不破哲三 古賀誠
幕下 二階伸康 前原誠司
幕下 木原誠二 千原せいじ
幕下 松原耕二 百田尚樹
幕下 松井一郎 村上春樹
幕下 山本一太 岡田直樹
幕下 舛添要一 猪瀬直樹
幕下 徳永信一 初鹿野弘樹
三段目 福永活也 内田樹
三段目 岡田克也 八代英輝
三段目 橋口かずや 苫米地英人
三段目 榛葉賀津也 鈴木大地
三段目 前田万葉 鈴木直道
三段目 枝野幸男 鈴木貴子
三段目 日枝久 佐藤正久
三段目 執行草舟 孫正義
三段目 木村草太 石平
三段目 草野仁 石濱哲信
三段目 宮路拓馬 石井彰
三段目 馬淵澄夫 石井孝明
三段目 馬場伸幸 石原伸晃
三段目 音喜多駿 石丸幸人
三段目 宮崎駿 石戸諭
三段目 北村晴男 有村治子
三段目 平野雨龍 有田芳生
三段目 平沢勝栄 嘉田由紀子
三段目 加藤勝信 小野田紀美
三段目 勝間和代 大田弘子
三段目 薬師寺道代 太田房江
三段目 羽賀ヒカル 太田光
三段目 大津綾香 大空幸星
三段目 大野泰正 大谷翔平
三段目 大野元裕 大谷光淳
三段目 大村秀章 大谷暢裕
三段目 津田大介 大谷昭宏
三段目 朝堂院大覚 中田宏
三段目 中田敦彦 中川宏昌
三段目 中条きよし 中山展宏
三段目 中谷元 中曽根弘文
三段目 竹中平蔵 吉村洋文
三段目 山中竹春 村井嘉浩
三段目 姜尚中 義家弘介
序二段 田中眞紀子 青山和弘
序二段 田久保眞紀 福島正洋
序二段 豊田真由子 安藤裕
序二段 倉田真由美 黒川弘務
序二段 世良公則 世耕弘成
序二段 岸信千世 岸博幸
序二段 岸口実 原口一博
序二段 浜田靖一 石原宏高
序二段 新田哲史 上脇博之
序二段 新浪剛史 三木谷浩史
序二段 養老孟司 鮫島浩
序二段 森下千里 馳浩
序二段 森健人 森屋宏
序二段 森喜朗 森山裕
序二段 森康子 森内浩幸
序二段 森まさこ 宮沢孝幸
序ノ口 我那覇真子 与国秀幸
序ノ口 忽那賢志 東国原英夫
序ノ口 西岡力 岡秀昭
序ノ口 福岡政行 尾身茂
序ノ口 井上正康 中曽根康隆
序ノ口 上昌広 足立康史
序ノ口 上念司 安達悠司
序ノ口 下地幹郎 西田昌司
序ノ口 下村博文 西村康稔
序ノ口 木村太郎 反町理
序ノ口 杉村太蔵 鈴木敦
序ノ口 藤村晃子 茂木敏充
序ノ口 吉村作治 吉野敏明
序ノ口 有吉弘行 芳野友子
序ノ口 北野武 南部智子
序ノ口 北野裕子 中田優子
序ノ口 安藤優子 小渕優子
序ノ口 安野貴博 松野明美
序ノ口 松野博一 稲田朋美
序ノ口 松山千春 畝本直美
序ノ口 松本純 本間奈々
序ノ口 松原仁 松沢成文
序ノ口 松あきら 松島みどり
前相撲 安倍昭恵 松田学
前相撲 安積明子 岩田明子
前相撲 安住淳 牛田茉友
前相撲 ASKA YOSHIKI
前相撲 GACKT ガーシー
以下省略(敬称略)
「生きる条件」ニーチェの話を題材にして考える
「何びともお前のために、まさにお前が生の河を
渡ってゆくべき橋を架けることはできない。それ
ができるのは、お前ひとりのほか誰もいないので
ある」
フリードリヒ・ニーチェ著
『反時代的考察』(1876)
「私よりも宣告を申し渡した貴方達の方が
真理の前に恐怖に震えているじゃないか」
参考
2025.5.29
芸術作品は、うっぷん晴らしではなく
「人生観、情緒、内的現実を表現する」
『絵はすぐに上手くならない
デッサン・トレーニングの思考法』
(彩流社、2015)
2025.6.20
参考
当講座記事NO.397から
2025.4.16 福永かおるさん
ワタナベケンタロウさんと福岡方言での対話
青山透子・森永卓郎氏の事故原因説への疑問
中曽根康弘首相は乗員乗客救助の米軍の申し出を断わり、
かつ即座に救助の陣頭指揮を取らなかった。最大の問題。
人命尊重の真心、感情、精神、思想、政治理念に欠ける。
ある意味日本一の高校、ここの出身者で
明治以降の日本を創ってきたとも言える。
2025.4.17 福永かおるさん
組合問題、B 737max の危険性などに応える。
フジテレビはじめ日本企業の体質にも繋がる。
JAL123 事故、原発事故、万博会場事故等の
最大要因は、いずれも利権最優先にした故の
設計・施工ミスであったのではないだろうか。
(当講座編集人)
2025.6.16
2025.6.11
2025.6.6
『実存主義とは何か』
(人文書院、1996)
2025.6.3・4
〈小社推薦論文〉
カント『純粋理性批判』(1781年)
〈小社推薦図書〉
岩崎武雄著『正しく考えるために』
(講談社現代新書、1972)
岩崎武雄著『辯證法 -その批判と展開-』
(東大学術叢書、1954)
西田哲学批判
マルクス主義哲学批判
ヘーゲルの弁証法
キェルケゴールの弁証法
存在の弁証法
認識の弁証法
自覚の弁証法
「弁証法は現在では一般に矛盾の論理すなわち
形式論理学に言う矛盾律を否定する全く新し
い論理として考えられているが、実はここに
われわれの検討すべき根本的な点が存在して
いるのではないかと思うのである。」
「弁証法論者達がこの点を全く看過してひたす
ら弁証法を以て全然矛盾律を否定する新しい
論理であると考え、これこそ一切の問題を解
決する強力な論理であるとなしているのは極
めて非哲学的な態度であると言わねばならな
い。」
chazzさんのnote
2025.4.24
『現象学』
(勁草書房、1985)
米盛裕二著『アブダクション
仮説と発見の論理』
(勁草書房、2007)
2023.12.30
「新しい理論があらわれると、まず、不合理だと
いって攻撃される。次に、それは真理だと認めら
れるが、わかり切ったことで取るに足らないこと
だといわれる。最後に、それはきわめて重要なも
のになって、初めにそれに反対した人々も、その
理論は自分たちが発見したのだといい張るまでに
なってくる。」
ジェームズ氏の言われるとおりではあるが、
普遍性あるものであれば、そのような形で
広められることが普遍性や普遍性に近いこ
との証左となり、むしろ喜ぶべきことでは。
結果に貢献できればそれでよいと考えるが。
広めている人や広められている人の人間性
が問われるにしても。 (当講座編集人)
2025.5.24
『予測する心』
(勁草書房、2021)
2025.5.25
2025.5.27
2025.5.30
芸術作品は、うっぷん晴らしではなく
「人生観、情緒、内的現実を表現する」
参考
note、obakeweb
S.K.ランガー著
『シンボルの哲学』
(岩波文庫、2020)
S.K.ランガー著
『芸術とは何か』
(岩波新書、1967)
2025.4.7
2025.4.23
参考
2025.3.17
カトリーヌ・マラブー著
『ヘーゲルの未来
可塑性・時間性、弁証法』
西山雄二訳
(未来社、2005)
『泥棒! アナキズムと哲学』
(青土社、2024.7)
2025.4.24
『現象学』
(勁草書房、1985)
米盛裕二著『アブダクション
仮説と発見の論理』
(勁草書房、2007)
2025.5.17
当講座記事NO.401、394から
2025.5.17 木偶乃坊写楽斎さん撮影
きょうの大公孫樹
2025.5.18
2025.5.17 毎日新聞
マウリシオ・ラブフェッティ著
(プレジデント社、2023)
『人イヌにあう』小原秀雄訳
(ハヤカワ・ノンフィクション文庫、2009)
当講座記事NO.373から
2024.12.27 大人の国語便覧、うえのあいさん
一葉が失恋した妹に贈った和歌
いでや君などさは寝ぬぞぬばたまの
夜は闇ぞかし世は闇ぞかし
年のはじめ戦地にある人をおもひて(1895年)
おく霜の消えをあらそふ人も有を
いははんものかあら玉のとし
敷嶋のやまとますらをにえにして
いくらかえたるもろこしの原
「どうして私をお札なんかに、腹立ちますわ」
右から一葉、母たき、妹くに森鷗外の一葉葬儀馬上参列を断った妹は立派
2025.1.1 ドンマッツさん
人類の最大課題
声なき声を聴く
男性は家事労働から始めよ
『10代から知っておきたい
女性を閉じこめる「ずるい言葉」』
(WAVE出版、2023)
当講座記事NO.274、375から
優曇花の朝 日の出直前の仏島と富山湾
氷見と七尾の県境 山並みの先は糸魚川
これから糸魚川の海岸辺りから陽が昇る
朝焼けの紫が紅色に溶け込んでいく
2019.4.5 木偶乃坊写楽斎さん撮影
『ラ・ロシュフコー箴言集』
二宮フサ訳
(岩波文庫、1989)
「祖国とは国語だ」
『ジェルミナール』
(1885)
2025.1.23 現代ビジネスのスクープ
2025.2.10・11
note、obakeweb
S.K.ランガー著
『シンボルの哲学』
(岩波文庫、2020)

S.K.ランガー著
『芸術とは何か』
(岩波新書、1967)
237 当講座登場作家とその作品・書籍紹介
2025.2.27
2025.2.28
2025.3.1
2025.3.2、3.3、3.4
当講座記事NO.280から
『わたしはわたし』
(求龍堂、2020)
熊谷守一埋葬場所(映像あり)
小村大樹さんブログ「歴史が眠る多磨霊園」から
「歴史が眠る多摩霊園」
小村大樹著
『歴史が眠る多磨霊園』
(花伝社、2019)
2025.3.11
飯盛元章著
『暗黒の形而上学
触れられない世界の哲学』
(青土社、2024)
2025.3.17
カトリーヌ・マラブー著
『ヘーゲルの未来
可塑性・時間性、弁証法』
西山雄二訳
(未来社、2005)
「何かを為せ、繰り返し為せ、朝から晩まで為せ、
寝ているときは夢を見よ、そして、それを立派に
為すことだけを、ほかならぬ私一人にできる限り
立派に為すことだけを、ひたすら考えよ」ニーチェ
国を守ること、家族を守ることとは
参考
当講座記事NO.356から
2024.8.15 TBS
鹿児島の特攻資料館を見学することは何ら批判される
ことではない。行って見てみることは何の問題もない。
どこにでも行って、見て、学ぶことはできるのである。
問われるのは、資料館の在り方や自分自身の生き方や
特攻隊や戦争をどのように考えたかということである。
また、早田選手の発言を批判・賛同する人がいるなら、
その理由を述べるべきである。そして対話すればよい。
(当講座編集人)
特攻兵の出撃を見送る知覧高等女学校の
生徒たち(1945.4.12・撮影 毎日新聞)
当講座記事NO.182、264から
〈小社推薦図書〉
(岩波文庫、1995)

プラトン著『パイドロス』(藤沢令夫訳、岩波文庫、1967)
ソクラテスは、本を書かない。
(書いたのは、プラトンである)
心を開いて通わせて対話する。
生きた智慧が互いに飛び交う。
2024.7.18 当講座記事NO.348から
戦後、校長はじめ教員はその後どうしたのだろうか
国家の要請に応える姿勢、体質だけは一貫している
「ススメ ススメ ヘイタイ ススメ」
〈小社推薦論文〉
当講座記事NO.208、226から
松永知子さん(金沢大学4年)の
卒業論文
カントの幸福論
カント『純粋理性批判』(1781年)
カント『実践理性批判』(1788年)
カント『判断力批判』(1790年)
当講座記事NO.274から
この説法を何と聴けばいいのか
カントの「物自体」の内実かも
「主観的感情の客観化」
「熟考もしくは理解を促す可能性をもつもの」
ひとりひとりが自分の思想をもつことが大切
(ちくま文庫、1997)
参考
当講座記事NO.300、佐藤章さんの解説から
憲法記念日に相応しい気合いが入った核心の憲法解説
またしても感涙
鈴木安蔵「憲法草案要綱」起草 (1945.12.26 官邸提出) ジョン・ロック. ジャン=ジャック・ルソーの思想が源泉
イギリス経験論
憲法は、「国民が天皇、摂政、政府、国務大臣、政治家、
裁判官その他の公務員に対して突き付ける命令書」である。
日本国憲法第54条第2項
衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。
但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊
急集会を求めることができる。
日本国憲法第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公
務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。
進次郎総理になると純一郎の二の舞い
生きることを簡単にするには
才能や能力から離れることだ。
常に心の動きには自由がある。
斎藤元彦兵庫県知事の問題は考え直すべきである。
他人の犠牲にならない生き方
他人を犠牲にしない生き方
藤森かよこ訳
(ビジネス社、2004)
人間とはなにか
『絵はすぐに上手くならない
デッサン・トレーニングの思考法』
(彩流社、2015)
「新しい理論があらわれると、まず、不合理だと
いって攻撃される。次に、それは真理だと認めら
れるが、わかり切ったことで取るに足らないこと
だといわれる。最後に、それはきわめて重要なも
のになって、初めにそれに反対した人々も、その
理論は自分たちが発見したのだといい張るまでに
なってくる。」
ジェームズ氏の言われるとおりではあるが、
普遍性あるものであれば、そのような形で
広められることが普遍性や普遍性に近いこ
との証左となり、むしろ喜ぶべきことでは。
結果に貢献できればそれでよいと考えるが。
広めている人や広められている人の人間性
が問われるにしても。 (当講座編集人)
当講座記事NO.274から、阿部信幾さん
当講座記事NO.279から
『意思と表象としての世界』(1819)
「人間はすべて理性あるものは同胞であること、
また、あらゆる人の世話をすることが人間の
自然の性にかなうことである」
「生きる条件」ニーチェの話を題材にして考える
「何びともお前のために、まさにお前が生の河を
渡ってゆくべき橋を架けることはできない。それ
ができるのは、お前ひとりのほか誰もいないので
ある」
フリードリヒ・ニーチェ著
『反時代的考察』(1876)
「私よりも宣告を申し渡した貴方達の方が
真理の前に恐怖に震えているじゃないか」
「芸術の本質は感情の表現である」
「生きる本質は信念の表出である」
井奥陽子著『近代美学入門』
(ちくま新書、2023)
制作物の制作者の意図に普遍性が含まれているか
『哲学のきほん』(岡本朋子訳)
(早川書房、2017)
当講座記事NO.348から
2024.6.30 毎日新聞
(鼓直訳、新潮社、2024.6.26)
当講座記事NO.302、311、319、328から
読書でしか得られない価値
マリア・コダマ・シュヴァイツァーとボルヘス
「粘土塀」改題『終わりし道の標べに』(1948)
『少女と魚』(戯曲、1953)
『兵士脱走』(ラジオドラマ、1957)
過去を呼び覚ます記憶、精神の力
「知性」は「勇気」の下僕である
文字なき世の人々の心を読む宣長
本を書かなかったソクラテス、本を書いたプラトン
「話す」ことと「書く」ことの違い
『パイドロス』心を開いて通わせ
対話する。生きた智慧が飛び交う。
本当の思想的・学問的論争とは
戦前の日本におけるマルクス主義の二大潮流
講座派と労農派について
2024.7.6 本物の保守とは
山崎行太郎著『小説山川方夫伝』
(反時代出版、2024.7.27)
自著紹介
日中国交正常化の影の立役者・木村武雄
『木村武雄の日中国交正常化』
(望楠書房、2022)
きいている
あのおじさんはきっと
好い人にちがいない!
気仙沼と全世界の
図書館さまへ
阿部信幾さん
〈小社推薦図書〉
岩崎武雄著『正しく考えるために』
(講談社現代新書、1972)
岩崎武雄著『辯證法 -その批判と展開-』
(東大学術叢書、1954)
西田哲学批判
マルクス主義哲学批判
ヘーゲルの弁証法
キェルケゴールの弁証法
存在の弁証法
認識の弁証法
自覚の弁証法
「弁証法は現在では一般に矛盾の論理すなわち
形式論理学に言う矛盾律を否定する全く新し
い論理として考えられているが、実はここに
われわれの検討すべき根本的な点が存在して
いるのではないかと思うのである。」
「弁証法論者達がこの点を全く看過してひたす
ら弁証法を以て全然矛盾律を否定する新しい
論理であると考え、これこそ一切の問題を解
決する強力な論理であるとなしているのは極
めて非哲学的な態度であると言わねばならな
い。」
当講座記事NO.311から